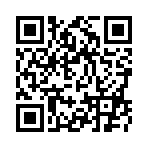2024年04月26日
2023年10月13日
海上釣堀 辨屋
10月13日 晴 (大潮)
三重県度会郡南伊勢町礫浦
海上釣堀 辨屋
三重県度会郡南伊勢町礫浦
海上釣堀 辨屋
〔閑人の釣果〕 12
シマアジ 3 (シラサ2・ダンゴ1)
マダイ 6 (シラサ2・ダンゴ2・アマエビ2)
イサキ 3 (シラサ2・ダンゴ1)
シマアジ 3 (シラサ2・ダンゴ1)
マダイ 6 (シラサ2・ダンゴ2・アマエビ2)
イサキ 3 (シラサ2・ダンゴ1)
2023年07月10日
2023年05月15日
2023年03月23日
2023年02月04日
2022年12月09日
2022年11月09日
でくのぼう
木偶乃坊こけし
南部系 キナキナこけし
煤孫盛造 6寸
南部系 キナキナこけし
煤孫盛造 6寸

外套に帽子をかぶった宮沢賢治の姿
岩手県花巻の伝統こけしと郷土の偉人の姿が融合する
作者は南部系キナキナこけし工人の煤孫盛造(すすまごもりぞう)
名付けて「木偶乃坊(でくのぼう)こけし」
宮沢賢治の詩「雨ニモマケズ」でお馴染みのデクノボー(木偶の坊)
木偶の坊とは、人形・あやつり人形・役に立たない人・気のきかない人を意味する
又、東北地方ではこけしを「でくのぼう」と呼ぶこともある
花巻農学校教諭時代の宮沢賢治の写真が残されている
帽子をかぶり田の中に立ち地面を見つめる姿
その賢治の姿を表現したロクロ木地のオブジェ
煤孫こけし三代目煤孫盛造が考案した新意匠のデザイン
花巻の風土と伝統の匠の技が生み出す郷土色豊かな素朴なこけし
本こけしは山梨材を使った17.8cm(6寸)の作品
岩手県花巻の伝統こけしと郷土の偉人の姿が融合する
作者は南部系キナキナこけし工人の煤孫盛造(すすまごもりぞう)
名付けて「木偶乃坊(でくのぼう)こけし」
宮沢賢治の詩「雨ニモマケズ」でお馴染みのデクノボー(木偶の坊)
木偶の坊とは、人形・あやつり人形・役に立たない人・気のきかない人を意味する
又、東北地方ではこけしを「でくのぼう」と呼ぶこともある
花巻農学校教諭時代の宮沢賢治の写真が残されている
帽子をかぶり田の中に立ち地面を見つめる姿
その賢治の姿を表現したロクロ木地のオブジェ
煤孫こけし三代目煤孫盛造が考案した新意匠のデザイン
花巻の風土と伝統の匠の技が生み出す郷土色豊かな素朴なこけし
本こけしは山梨材を使った17.8cm(6寸)の作品
「煤孫こけし」は祖父茂吉、父実太郎、私盛造と三代にわたって伝承されてまいりました。このこけしは、伝統こけし南部系(花巻系)に属し無彩色で頭がクラクラ動くのを特徴としております。
昔、乳児のおしゃぶりとして与えれていた、頭が小さく胴の下部がくびれたこけしをはじめ胴の上部がくびれたこけし等を造っております。また、牡丹の花を絵付けしたこけしもございます。これらのこけしは、この地方でキックラボッコキナキナボッコの方言で呼ばれております。
材料は、主にコサンバラ(モチノ木科アオハダ・白い木目の見えない木)を使用します。その他ケヤキ・エンジュ・タモ・サクラ・ヤマガ・クワ等を使います。木目の美しいケヤキなどを使用したこけしは、頭と胴を一本の木から作りますので木目がピッタリと合いますように造って居ります。
この「木偶乃坊こけし」は岩手の山々に育まれた木々を素材にして造られております。木々の種類により木肌の色合い木目の違いがありますので一つ一つこけしの雰囲気が異なっております。このこけしにそれぞれの賢治の世界を想い描いて楽しんで頂ければ幸いと存じます。
-「工房 木偶乃坊」HPから-
2022年11月05日
一寸こけし
佐藤英次 1寸
寸法2.9cmの小寸ながら、典型的な遠刈田系のこげすの形態を呈している
肩のこけた造り付けの胴には襟描きの梅模様
つぶし目に割れ鼻でちょぼ口の面相、頭は古風な蝶形手柄
作者は遠刈田系周治郎系列の佐藤(朝倉)英次(当時22歳位)
昭和8年頃の遠刈田温泉北岡商店の豆こけしである
鈴木鼓堂コレクション『愛玩鼓楽』1376番の現品
肩のこけた造り付けの胴には襟描きの梅模様
つぶし目に割れ鼻でちょぼ口の面相、頭は古風な蝶形手柄
作者は遠刈田系周治郎系列の佐藤(朝倉)英次(当時22歳位)
昭和8年頃の遠刈田温泉北岡商店の豆こけしである
鈴木鼓堂コレクション『愛玩鼓楽』1376番の現品
2022年10月22日
海上釣堀 はさま浦釣り堀センター
10月22日 晴 (中潮)
三重県度会郡南伊勢町迫間浦
海上釣堀 はさま浦釣り堀センター
三重県度会郡南伊勢町迫間浦
海上釣堀 はさま浦釣り堀センター
〔閑人の釣果〕 4
カンパチ 1 (活アジ)
ワラサ 1 (活アジ)
マダイ 2 (アオムシ・シラサ)
カンパチ 1 (活アジ)
ワラサ 1 (活アジ)
マダイ 2 (アオムシ・シラサ)
2022年09月17日
2022年06月24日
2022年05月20日
海上釣堀 辨屋
5月20日 曇 (中潮)
三重県度会郡南伊勢町礫浦
海上釣堀 辨屋
三重県度会郡南伊勢町礫浦
海上釣堀 辨屋
〔閑人の釣果〕 8
ヒラマサ 2 (活きアジ・コウナゴ)
カンパチ 1 (シラサ)
マダイ 5 (ダンゴ2・シラサ2・コウナゴ1)
ヒラマサ 2 (活きアジ・コウナゴ)
カンパチ 1 (シラサ)
マダイ 5 (ダンゴ2・シラサ2・コウナゴ1)
2022年04月21日
海上釣堀 辨屋
4月21日 曇のち雨 (中潮)
三重県度会郡南伊勢町礫浦
海上釣堀 辨屋
海上釣堀 辨屋
〔閑人の釣果〕 11
ヒラマサ 1 (活きアジ)
マダイ 9 (ダンゴ4・シラサ3・アカムシ2)
サクラマス 1 (シラサ)
ヒラマサ 1 (活きアジ)
マダイ 9 (ダンゴ4・シラサ3・アカムシ2)
サクラマス 1 (シラサ)
2021年12月20日
2021年10月11日
2021年04月16日
2020年11月13日
2020年09月23日
海上釣堀 辨屋
9月23日 曇り(時々雨) (小潮)
三重県度会郡南伊勢町礫浦
海上釣堀 辨屋
三重県度会郡南伊勢町礫浦
海上釣堀 辨屋
〔閑人の釣果〕 8
カンパチ 1 (活アジ)
マダイ 4 (ダンゴ2・シラサ1・ササミ1)
イサキ 3 (シラサ2・ササミ1)
カンパチ 1 (活アジ)
マダイ 4 (ダンゴ2・シラサ1・ササミ1)
イサキ 3 (シラサ2・ササミ1)
2020年02月13日
海上釣堀 傳八屋
2月13日 晴 (中潮)
三重県度会郡南伊勢町迫間浦
海上釣堀 傳八屋
三重県度会郡南伊勢町迫間浦
海上釣堀 傳八屋
〔閑人の釣果〕 7
ワラサ 1 (活アジ)
マダイ 1 (シラサ)
イサキ 1 (ダンゴ)
クロソイ 4 (シラサ3・ダンゴ1)
ワラサ 1 (活アジ)
マダイ 1 (シラサ)
イサキ 1 (ダンゴ)
クロソイ 4 (シラサ3・ダンゴ1)