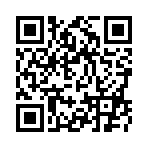2025年01月18日
倭姫命
倭姫命 (やまとひめのみこと)
倭姫命(やまとひめのみこと)は、第十一代垂仁天皇の皇女で、垂仁天皇二十五年三月に天照大神を伊勢の地(現在の伊勢神宮)に皇大神宮をご創設され、斎宮の起源となった人物である。
倭姫命は、第十一代垂仁天皇の皇女です。第十代崇神天皇の皇女豊鍬入姫命の後を継いで、「御杖代(みつえしろ)」として天照大神に奉仕され、天照大神を載いて大和国をお発ちになり、伊賀・近江・美濃などの諸国を経て、伊勢の国に入られて、御神慮によって、皇大神宮をご創設されました。
「御杖代」とは天照大神の御杖となって、御神慮を体して仕えられるお方の意です。倭姫命から後、代々の天皇は未婚の皇女を伊勢に遣わして天照大神に奉仕させられましたが、このお方を斎王(いつきのみこ)と申し上げます。
命は皇大神宮御鎮座ののち、神嘗祭をはじめとする年中の祭りを定め、神田並びに各種のご料品を奉る神領を選定し、禰宜、大物忌以下の奉仕者の職倭姫掌を定め、斎戒や祓の法を示し、神宮所属の宮社を定められるなど、神宮の祭祀と経営の基礎を確立されました。
後に第十二代景行天皇の五百野皇女に後を継がせ、東夷の討伐に向かう日本武尊(尊は倭姫命の甥王にあたる)に草薙剣を授けている。伊勢では、伊勢の地に薨じ、尾上御陵(おべごりょう)に埋葬されたと伝える。伊勢の地で天照大神を祀る最初の皇女と位置づけられ、これが制度化されて後の斎宮となった。
倭姫宮 (やまとひめのみや)
倭姫宮表鳥居 倭姫宮拝殿・本殿
-2010年11月撮影-
倭姫宮(やまとひめのみや)
創建年代 大正12年(1923)11月5日
鎮座地 三重県伊勢市楠部町5
御祭神 倭姫命(やまとひめのみこと)
倭姫宮は、皇大神宮(内宮)の別宮で、おまつりする神様は倭姫命(やまとひめのみこと)です。
倭姫命は天照大神の御神教(みおしえ)をうけて約二千年前に、五十鈴川の川上、現在の場所に皇大神宮をご創建されました。
大きなご功績をお遺しになられた命の御徳をお慕いして、大正の初年から神宮司庁と宇治山田市(現在の伊勢市)が命をまつるお宮の創建を請願してきましたが、大正十年一月四日、皇大神宮別宮として倭姫宮のご創立が許可され、同十二年十一月五日に御鎮座祭が執り行われました。
神宮には、別宮・摂社・末社・所管社の諸宮社があり、ご由緒は極めて古く、奈良時代以前に遡るものが多いのですが、倭姫宮は、創立が極めて新しいのです。
-倭姫宮御杖代奉賛会HPから-
倭姫命人形
上掲倭姫命人形は昭和5年に三重県宇治山田市で開催された『御遷宮奉祝神都博覧会』の協賛会の記念品である。
伊勢神宮に最も所縁のある人物として相応しい倭姫命が選ばれたのだろう。
日本武尊(ヤマトタケルノミコト)に宝剣(草薙剣)を授け賜う倭姫命のお姿を表した木目込み人形(ガラスケース入)である。
景行天皇の御代、日本武尊が東征の折に伊勢神宮に参拝し、叔母の斎宮倭姫命から神宝草薙剣を授けられるという『記紀』に載る有名な物語の一場面である。
御遷宮奉祝神都博覧会の歴史館では同場面のジオラマも展示され、絵葉書も発行された。
歴史館ジオラマの絵葉書

御遷宮奉祝神都博覧会
御遷宮奉祝神都博覧会鳥瞰図 吉田初三郎作

昭和4年秋の伊勢神宮遷宮のあとを受けて、全国から新造の神宮参拝が増加するのを機に神宮周辺を神都とする構想もあり、奉祝記念事業としても、観光振興の好機と開催。会場は宇治山田市の度会郡役所跡で、正面中央に本館、農林館、国産館が主要パビリオンとして建てられ、国産館内部には3府32県からの出品が展示された。御大典に使用された御物や勲章などを陳列した御物館や、神代からの歴史を18面のジオラマにした歴史館がつくられた。これは大礼記念館と合わせて神都記念館として閉会後も遺された。また、大阪の朝日新聞社と毎日新聞社が展示スペースを設け、電光ニュースや活動写真を上映するなど両社が競って気を吐いた。一方、北海道館、樺太館、台湾館、朝鮮館、満蒙館などが単独の展示館として出展した。このほか有料の御遷宮記念館では遷宮の状況や神宮の由緒をジオラマで見せた。名物館では江戸時代の伊勢参りの様子を再現し、名勝館では伊勢近辺の景色を段返し式キネオラマで見せた。演芸館は地元芸妓連の伊勢音頭や七福神踊りを上演して賑わった。また、場内イベントとして実際の宇治橋の模型橋が作られ、昔の投げ銭の風俗を体験させた。不況下にもかかわらず、72万人が入場した。
-博覧会資料COLLECTION HPから-
中央噴水塔 北海道館


いかばかり 涼しかるらん 仕へきて
御裳濯川を 渡る心は 西行
いすず川 影見る水も 底すみて
神代おぼゆる 峯の杉むら 本居宣長
この記事へのトラックバックURL
http://manyuuki.mediacat-blog.jp/t156200